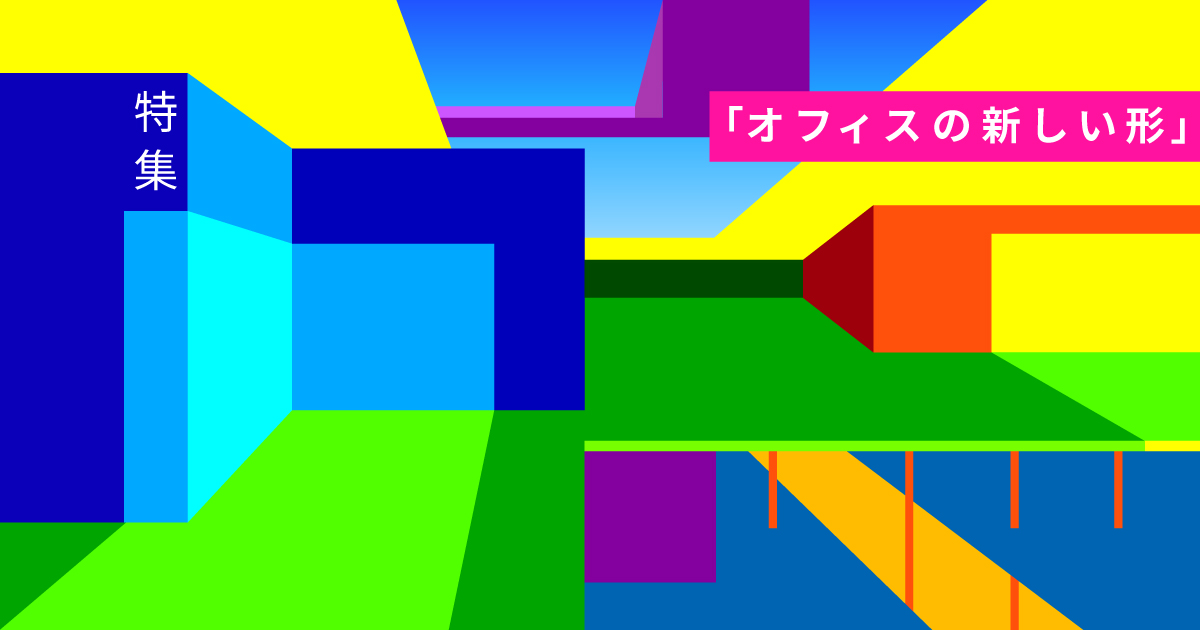
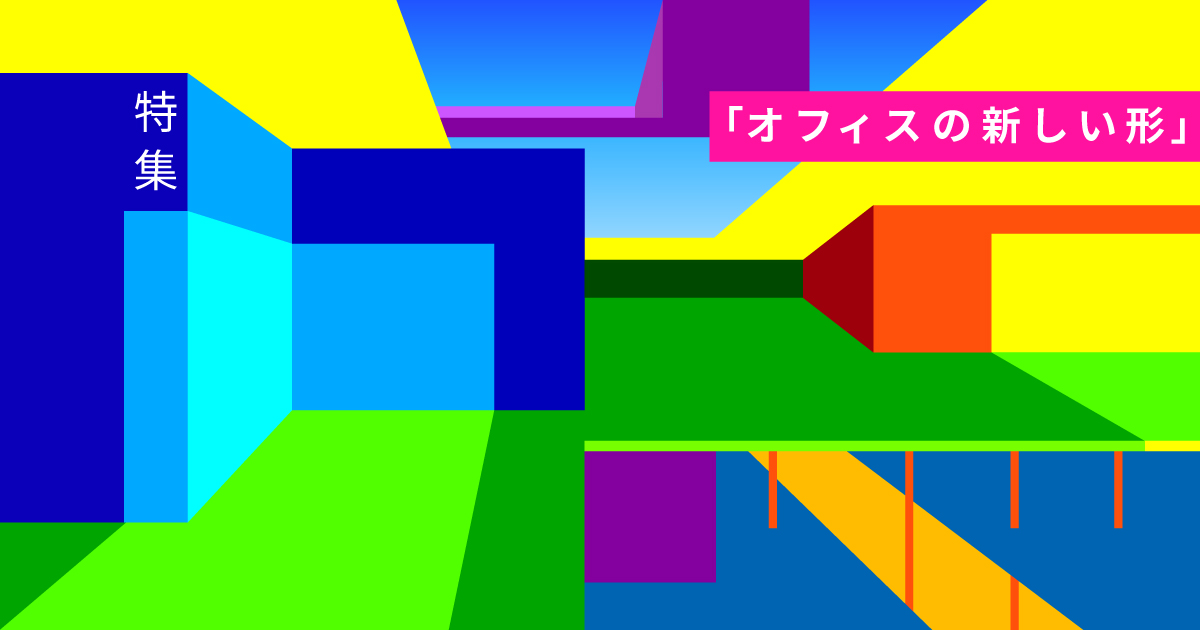
ビジュアルデザイン:南田真吾
公開日:2025/09/12
特集
空間づくりに関わる企業が取り組む「オフィスの新しい形」
テレワークやフレックスタイム、時短勤務、副業など、多様な働き方が急速に広まっているいま。“オフィスの形”にも、柔軟さと機能性が同時に求められている。
そうした流れの中で、空間に関わる企業はどのような“オフィスの新しい形”をつくり上げているのか。本特集では、編集部が厳選した5社の取り組みを紹介する。
株式会社サンゲツ「PARCs Sangetsu Group Creative Hub」
インテリアからエクステリアまで人々の暮らしを彩る商品を生み出すインテリア総合企業のサンゲツグループは、2024年1月10日に発表した新たな企業理念に加え、長期ビジョン【DESIGN 2030】、そして中期経営計画【BX 2025】に掲げる成長戦略に基づき、強固な収益力と成長力を持つ“スペースクリエーション企業”への転換を目指している。
今後さらに成長戦略を加速させ、あらゆる「空間」をクリエイティブな感性でデザインし提供する“スペースクリエーション企業”への転換を実現することを目的に、東京に新たな価値創造の場としてのオフィスをつくることとなった。
設計のポイントの1つになったのが、「多様なアクティビティが生まれ、ウェルビーイングに配慮した空間設計」。社員と来訪者が自由に集い、交流できる公園のようなランドスケープが広がるオフィスとして、本物の植物をふんだんに使い、社員の健康促進とエンゲージメントの向上を目指した。設計にあたっては、新しい働き方やオフィスをどうしていきたいかを全社横断型ワークショップを開催して課題を抽出し、社員のアイデアや考え方を取り入れている。

「PARCs Sangetsu Group Creative Hub」の内観
新オフィス「PARCs Sangetsu Group Creative Hub(以下、PARCs)」は、日比谷公園を眼前にのぞむ快適なロケーションを生かしながら、多種多様なヒト・モノ・コト・情報が集まる公園・広場のようなオフィスを目指し、ウォーカブルオフィスとして空間を構成。「touch the prism」をコンセプトに、ジグザグと角度をつけた通路やランダムに配置されたファシリティなど、偶発的な会話やアイデアが生まれる工夫を凝らされている。
また、各エリアには実践的素材・環境に配慮した素材など、新素材を積極的に導入することでさまざまな新しい可能性を生み出し、情報を発信していく場ともしている。そのほか、ウェルビーイングを取り入れた働き方を実現するため、例えば、人間の体内時計に合わせて照明の色温度や明るさを調整するサーカディアン照明を取り入れるなど、オフィス環境を整備することで「WELL認証」ゴールドを取得している。

床材には廃材を活用した「複層リサイクルタイル」、テーブル天板にはサンゲツの壁紙の廃材を再利用した「廃棄壁紙リサイクル人工大理石」を使用している
PARCsは、サンゲツグループの商品・空間デザイン機能、多岐にわたる空間提案といったさまざまな機能が、集まり・つながり(Connect、Collaboration)、新たな創造力 (Creativity) のもと、常に果敢に変化し、チャレンジ (Courage、Change、Challenge) し続ける場となっている。PARCsの名称は「Parade of Cs」に由来しており、さまざまな“C”が集い、まるでパレード(Parade)のような活気にあふれた空間を目指している。

階段部分には、PARCsの由来である「Parade of Cs」を表現している
同オフィスをオープンさせたことによって、他部署の働き方が見えるようになり、会社全体の理解に繋がっている。また、社員同士の接点が生まれ、「Parade of Cs」のさまざまな“C”が空間に息づき、より豊かなコミュニケーションが生まれている。また、サンゲツグループとしてのシナジーを発揮した空間デザインの提案も加速している。
写真:Akihiro Itagaki(Nacása & Partners)
【求人内容】
職種:空間デザイナー
雇用形態:正社員
勤務地:全国
求人情報詳細:https://jobs.japandesign.ne.jp/recruit/1580
株式会社アクタス 本社 LIVE OFFICE「THINK PORTAL」
長年にわたり「心地よい暮らし」を提案してきたアクタス。その豊富な知見やデザイン力をオフィス空間にも応用し、自社の本社オフィスを「未来の働き方を体現する実験の場」と位置づけて、社員の創造性を最大限に引き出す空間へとリニューアルすることとした。
そして、本社オフィス「THINK PORTAL」が誕生。このリニューアルプロジェクトで培ったノウハウを活かし、オフィスコントラクト事業への本格参入も決めたという。

「THINK PORTAL」という名称には、「社員一人ひとりの思考(THINK)が、社内外の様々な情報や人々と活発に交差し、新たな価値を生み出す入り口(PORTAL)となる」という想いが込められている。このコンセプトを実現するため、単に内装を新しくするだけでなく、社員の働き方そのものを変革することを目指した。
プロジェクトでは、社員の固定席を撤廃し、フリーアドレスを導入。さらに、その日の業務内容や気分に合わせて、最も集中できる、あるいは最もコミュニケーションが取りやすい場所を自ら選んで働く「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」という考え方を取り入れ、訪れる人の目的や気分に応じて使い分けられる3つのエリアで構成されている。
1つ目は、集中とリラックスを両立させ、創造性を高めることを目的としたエリア「PORTAL WEST(クリエイティブエリア)」。日本初導入の海外ブランド家具など、デザイン性と機能性に優れた家具が配置され、ソロワークに没頭できる静かなブースから、複数人で議論を戦わせるミーティングスペース、アイデアを創出させるライブラリースペース、ソファで寛ぎながら談笑できるラウンジなど多様な機能を持っている。
2つ目の「PORTAL EAST(本社機能エリア)」は、本社機能が集約された、実務中心のエリア。こちらもフリーアドレスで、収納家具を兼ねたカウンターで空間をゆるやかにゾーニングしている。数カ所に軽いミーティング時などに活用できるスタンドタイプのコミュニケーションスペースを設けた、機能的なレイアウトとなっている
3つ目の「RECEPTION FLOOR(対面と交流のフロア)」は、ガラスパーテーションで仕切られた開放的な応接・会議スペース。各部屋は同社が取り扱う国内外の家具でコーディネートされている。全体として、自然素材の造作家具や床、デザイン性の高い照明、グリーンなどが効果的に配置され、心地よさと機能性を両立させた空間となっている。

「PORTAL EAST」エリア
固定席をなくし、オフィス内を自由に回遊できるようにしたことで、部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションが増加。何気ない雑談からビジネスのヒントが生まれるなど、偶発的な出会いがイノベーションを促進している。
また、その日の気分や業務内容に合わせて自律的に働く場所を選べるようになったことで気分転換が図れ、仕事へのモチベーション向上に繋がっている。
そのほかにも、オフィスが魅力的になったことで、社員の会社に対する愛着や誇りが深まっている。社員の発案で家族をオフィスに招く「ACTUS OPEN DAY」が開催されるなど、オフィスが社員と会社、そして社会とを繋ぐプラットフォームとしての役割も担いはじめている。
【求人内容】
職種:
・システムキッチンやシステム収納、インテリア設計
・ホテルや宿泊施設を中心としたデザイナー
・グラフィックデザイナー(紙媒体/ネット広告など)
雇用形態:正社員
勤務地:東京都新宿区新宿(都営新宿線新宿三丁目駅C8出口より直結)
求人情報詳細:https://jobs.japandesign.ne.jp/recruit/1565
株式会社遠藤照明「Synca U/X Lab CROSS OSAKA」
数年におよぶコロナ禍を経て、リモートワークやWeb会議の定着による働き方の変化、ワークライフバランスへの意識の高まりにより、オフィスの存在意義が大きく変化した。
この変化を背景に、照明器具メーカーである遠藤照明は、企業理念である「光によって人をどこまで幸せにできるか」を検証するラボとしての役割を持ちながら、働く人の健康に寄与し、より快適に、より効率よく業務を遂行するための新しいオフィス兼ショールームをデザインした。
自然光を再現可能な次世代調光調色LED照明器具「Synca」を照明計画の基軸とし、自然光に限りなく近い光環境が人の生理・心理に与える影響に関するエビデンスを蓄積しながら、適時適光による省エネも追求。社員とお客さまがその効果を体感することによって、オフィスの価値、幸福度、生産性の向上に貢献できるインテリアと光のあり方を目指した。

「Synca U/X Lab CROSS OSAKA」3F。自然光を再現した照明「Synca」を基軸として、「光」のポテンシャルを追求した空間デザインを体感できる
同オフィスデザインの要は「光」。物質としての姿を持たない光を主役とすべく、内装色は黒、白のモノトーンと木目で構成。内装が背景の役割を担うことで、光色の変化を最大限に感じることができる。
照明計画では、照度や色温度による心理効果、ストレス軽減などのデータをもとに、仕事の内容、場所に応じた光環境を追求。さらに、時間によって光を変化させることで、屋内に自然光の移ろいを再現している。オフィスで働く人の時間への意識を高め、リフレッシュを促す効果を得ている。
大型植物を設置したリトリートゾーンでは、照明に加え、風通しを再現した空気還流機器によって、植物の育成と人を癒すバイオフィリックデザインを追求。社員アンケートからも生産性、幸福度の向上が実証されている。

リトリートゾーンでは、本物の植物を人工光のみで育成している(画像上:朝のシーン、画像下左:午後のシーン、画像下右:植物育成モード)
オフィスはショールームとしても公開されており、現在では3,000名を超えるさまざまな業種の人が体験し、多くの採用検討に繋げている。なお、同様のオフィス兼ショールームは、東京にある「Synca U/X Lab」でも体験できる。「Synca U/X Lab」は、大阪の「Synca U/X Lab CROSS OSAKA」に先駆けた2021年にオープンしており、2022年にグッドデザイン賞を受賞している。

東京にある「Synca U/X Lab」
株式会社乃村工藝社 未来創造研究所「Creative Lab.」
「空間創造によって人々に“歓びと感動”を届ける」をミッションに、空間の総合プロデュースをおこなう株式会社乃村工藝社。同社はこの「歓びと感動」を追求していくために、2022年に社内研究開発組織「未来創造研究所」を発足。自らのクリエイティビティを起点に外部クリエイターや企業を巻き込みながら、空間の価値をアップデートする研究・実装をおこなっている。
しかし、特定の活動場所を持たずにこれまでやってきた中で、活動に根を張れるリアルな場所がほしいという声が大きくなってきた。同時に経営側から、空間の未来を考え続けている乃村工藝社らしさが伝わるショールームが欲しいという要望もあり、これらを統合的に実現するためのプロジェクトがスタートした。
キーワードは「青臭い話をしよう」。雇用形態も多様化し、働く場所も限りなく自由になりつつある現代とはまさに逆行する、少し“濃すぎる”と感じる関係性の再構築を狙った。「研究」「発見」「交流」の3つの機能を同一空間で共存させ、自分たちでの運営や、日常的な仕事、プロトタイプ展示、社内外の人を招いてのイベントやワークショップなどのそれぞれのシーンが常に緩やかに混ざり合う空間を目指した。

未来創造研究所「Creative Lab.」
デザインしたのは空間ではなく、“空気感”。失敗が許されたり、人のプロジェクトにおせっかいで口を出し合えたり、あえて「帰属感」「家族のような空気感」を生み出すために、5つのポイントで設計をおこなった。
①お互いの気配がわかり、端から端にも声が届くよう、壁をつくらず、最適な抜け感を実現する“オリジナルユニット”によって全体を構築
②フリーアドレスでは難しくなっていた“活動の途中”の集積。これを可能にすることで多くの人に活動が見えるようになり、お互いのおせっかいを生み出す
③空間の一定の秩序を保ちつつも個々の自由が利く余白を確保。空間のベースとなるフレームだけを提供し、工夫脳のスイッチを常にONにしつつ、ここが自分のホームである意識を醸成
④みんなで集まるためのキッチンや床座の広間。「同じ釜の飯を食う」場所と時間を空間の核とする
⑤開発した天然木OAフロアを全面に敷設し、靴を脱いで過ごす。見た目や香りに加え、靴を脱ぐ行為が利用者のモードを切り替え、心から本音で語り合える場に
これらが総合的に作用することで、通りかかったメンバーがふと気づけば議論の輪に加わっていたり、仕事をしながらトークイベントを片耳で聞いたり、「ゆるくつながる」「偶然に出会う」構造を実現。特別ではないが、確実に関係性を耕すための“定常的な小さな波”が、日常の中に組み込まれ、ここならではの“空気感”がつくられる。各活動の集積展示による自社ショールーム機能を果たすのではなく、そこで活動する人の姿そのものが乃村工藝社のショールーミングになっている。

トークイベントでの様子
同施設ができたことによって同社では、各活動に圧倒的にドライブがかかりはじめ、改めて「リアルの場」の持つ力を強く感じ、活動の成果が目に見えるようになり、内容の理解が深まりやすくなったとのこと。活動に対する社内からの関心も増え、未来創造研究所のためだけのラボではなく、乃村工藝社グループ全体のラボでありたいという設立当初からの想いの実現に向けて、一歩ずつ充実させている。
【求人内容】
職種:デザイン職
雇用形態:正社員
勤務地:
・A.N.Dオフィス/東京都港区南青山(東京メトロ表参道駅より徒歩10分)
・北海道支店/北海道札幌市中央区北一条西(市営地下鉄南北線大通駅より徒歩3分)
求人情報詳細:https://jobs.japandesign.ne.jp/recruit/1591
株式会社ミラタップ「本社移転プロジェクト」
売上の拡大にともない、従業員数も増え、フレックス制度や在宅勤務を活用しても旧オフィスが手狭になったことからはじまった「本社移転プロジェクト」。さらなる事業拡大・人員増加が見込まれていたため、企業の成長にはこれまで以上のコミュニケーション活性化・一体感の醸成が必要であり、全員が同じフロアで働ける環境が必要不可欠だと考え、2024年12月にオフィス移転をおこなった。
新しいオフィスに選ばれたのは、“関西最後の一等地”と言われる「うめきたエリア」にオープンした「グラングリーン大阪」。このような一等地にオフィスを構えることで、企業としてのブランディング強化、従業員のモチベーション向上、そして優秀人材の確保に繋げたいと考えた。

新オフィスのコンセプトは、「“はたらく”も楽しく、美しく。」。ミラタップは「くらしを楽しく、美しく。」を経営理念に掲げている。一般的に“くらし”と聞くと仕事以外のすべての時間が想像されるが、同社は仕事の時間もくらしの一部であると考え、1日の大部分を占める勤務時間を楽しく、美しいものとできるよう、今回のオフィスデザインを考えたという。移転準備開始時には社内アンケートも実施し、従業員の声をもとに設計された。
新オフィスでは、床面積を旧オフィスの約1.5倍となる480坪に増床し、全従業員が顔を合わせて業務ができるよう、ワンフロアとした。ミラタップでは、在宅勤務比率は約4割であり、従業員は週2日の出社が義務付けられている。在宅勤務が当たり前となった昨今だからこそ、“出社する価値”を改めて見出したいと考え、ちょっとした打ち合わせができるスペースや、自然と人が集まる大きなキッチンを設けた。一部の部署を除いてフリーアドレス化したことで、部署の垣根を超えたコミュニケーションが増えたとのこと。
オフィス全体を“家”に見立てて設計しており、共同作業ができる「キッチンエリア」やリラックスして考え事ができる「バスルーム」、自然を感じられる「ダイニング」など、多様なエリアが設置されている。

社内のアンケートで最も要望が多かったのが「自社製品を使ってほしい」という意見。旧オフィスでは、自社製品が使われているエリアが少なく、部署によっては商品に触れる機会が少ないという課題があった。新オフィスの内装には、自社製品がふんだんに使用されている。自社製品でつくり上げられた空間を肌で感じることで、商品に対する愛着や誇り、仕事へのやりがいを高め、従業員のブランド・エンゲージメント向上を図っている。
今回のオフィス移転によって、取引先や友人・知人から褒められる機会が増え、出社が楽しく感じられる空間となった。




