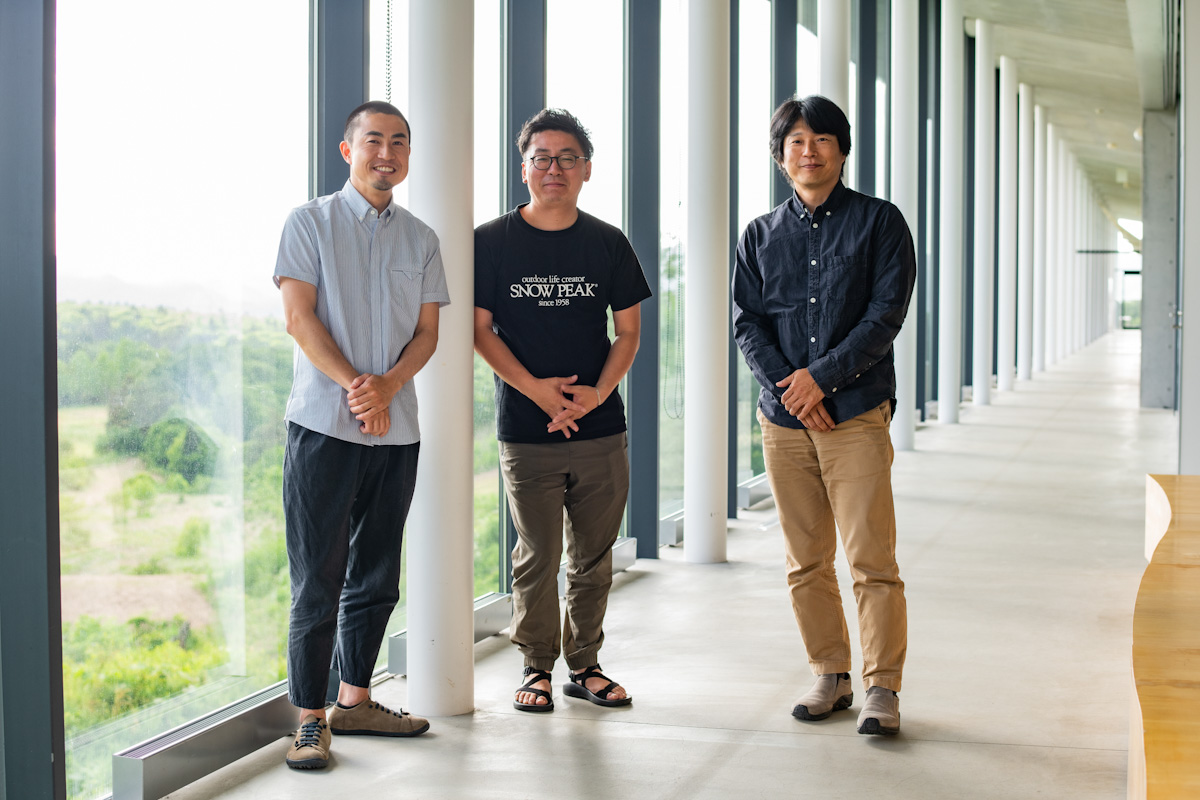
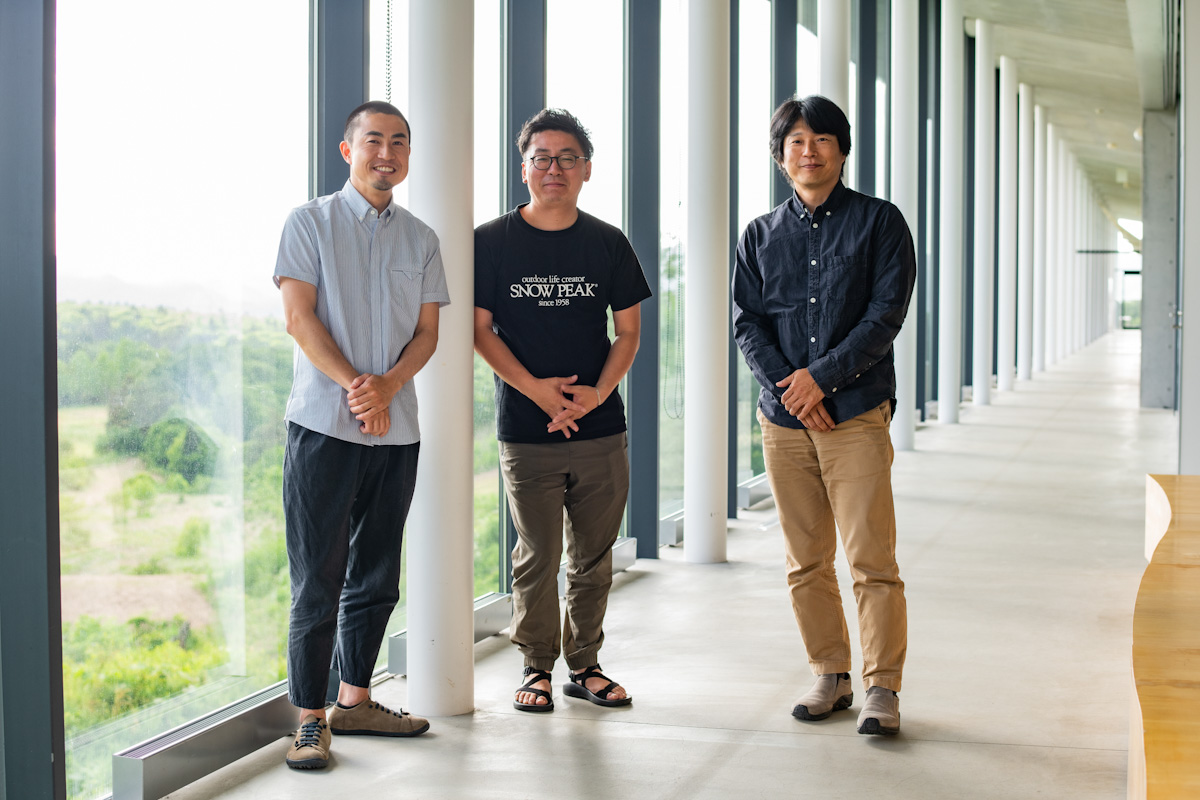
撮影:内藤雅子 取材・文:堀合俊博
公開日:2019/06/25
働き方インタビュー
PR
企画からデザイン、開発まで。「野遊び」をデザインするスノーピークの商品開発への情熱
株式会社スノーピーク
上山桂 執行役員 経営企画室長 CCPO 兼 経営管理本部長 CFO
林良治 執行役員 企画開発本部長 CPDO
吉野真紀夫 営業本部 東日本事業創造部 シニアマネジャー
「人生に、野遊びを。」をコーポレートメッセージにかかげ、アウトドア製品を中心に質の高いものづくりを実践するスノーピーク。近年はオフィスなどのビジネスシーンや、マンション、住宅地でのデザイン監修をおこなうなど、今年4月には、昨年「『デザイン経営』宣言」を発表した経済産業省・特許庁による「知財功労賞」を受賞し、経営におけるデザインの存在が高く評価されている。
新潟県燕三条を拠点とする同社は、地域密着型の企業としても知られている。アップルが引き合いに出される「デザイン企業」の商品開発はいかに行われているのか。キャンプ場に面したスノーピークの本社オフィスである「ヘッドクォーター」にて、企画開発本部長の林良治さん、経営企画室長の上山桂さん、営業本部シニアマネージャーの吉野真紀夫さんにお話をうかがった。

ユーザーから商品開発者に
――まずはそれぞれの経歴について教えてください。
林良治さん(以下、林):僕は今年で入社して12年目になりますが、スノーピークに入る前は東京のゲーム会社で働いていました。最初はプロダクトデザイナーとして、ゲーム機の本体をつくるところからスタートして、そこからかたちだけではなく中身もつくりたくなって、だんだんとデザイン以外のことも企画するようになりました。その後転々として、最後はカードゲームやおもちゃをつくっていましたね。
とても忙しい業界だったので、週末は息抜きに山や海、川に出かけていて、スノーピークのいちユーザーだったんです。子どもと一緒に家族でキャンプをしていて、スノーピークの製品に親しんでいるときから、「もっとこうしたらいいな」という思いがありましたね。

執行役員 企画開発本部長 CPDO 林良治さん
林:ゲーム業界にいたので、僕の仕事のテーマは「遊び」なんです。スノーピークは、違うステージで「遊び」を追求するアウトドア業界ですので、自分のデザインというスキルを生かして、面白いものができればいいなという思いから、入社しました。
入社当時は、会社のフィロソフィーそのものが全く違うので戸惑いもありましたけど、かたちあるものをつくるということは同じでしたし、むしろ扱ったことのない素材を使ったり、やったことがないデザインを経験できるので、楽しくやってましたね。
その後は一時期、サプライチェーンを管理する部門を担当し、現在はアウトドアギアの開発部門を担当しています。

営業本部 東日本事業創造部 シニアマネジャー 吉野真紀夫さん
吉野真紀夫さん(以下、吉野):僕は入社して16年目です。東京で生まれ育って、東京の下町の企業に就職して、7年くらいバッグのデザインをしていました。デザインだけじゃなく、布や皮を裁断したり、パターンを作ったり、職人みたいに自分の包丁を研いでました。そのあとマスマーケットのアパレル会社に転職して、デザイン部署のアクセサリーチームで、3年ほどバッグやアパレルアクセサリーを作っていました。
林さんと同じように、東京にいたときは僕も釣りやキャンプを毎週末のようにやっていたので、スノーピークは憧れの会社だったんです。僕は高くてあまり買えなかったんですけど(笑)。
スノーピークに入社したのと同時に、家族で新潟に移住してきました。環境はガラッと変わりましたね。毎週のようにキャンプにいく生活をしながら、開発をしていました。
現在は、東日本の法人営業部門で、マンションや住宅のデザイン監修やスタイル提案などを手がける「アーバンアウトドア事業」という新規事業を担当したり、フィッシングやペットといった新たな市場の可能性を広げることにも従事しています。
――移住される際に家族の反対はなかったんですか?
吉野:なかったですね。若いときの勢いというのもあって。うちの妻も東京の出身ですが、二人とも田舎暮らしの願望を元々持っていたんです。それまで新潟といえば、冬に湯沢あたりに滑りに来るくらいで、燕三条には来たこともなかったんですが、来てみたら自然の宝庫。もう最高ですね。
林:地元の人にとっては当たり前かと思うんですが、空気も水もよくて、農作物や海産物がおいしいんですよね。それって重要だと思います。
吉野:身近なところに自然があるので、会社へ行く前に釣りをするとか、就業後に釣りして帰るとか。そういうこともできますよね。

執行役員 経営企画室長 CCPO 兼 経営管理本部長 CFO 上山桂さん
上山桂さん(以下、上山):僕は大学でプロダクトデザインの勉強をしていて、スノーピークには新卒で入社しました。学生時代にはバックパッキングで島へ行ったり、キャンプをしたりしていて、スノーピークのことは、チタンのマグカップとか、小さいバーナーを作ってるメーカーという認識でした。
大学3年生のときに、周りが就職活動をしはじめる時期になって、自分もどうしようかなーっと……。社会性が非常に欠けていたので……(笑)。
林:当時は社内にそういう人たちいっぱい居ましたから(笑)。
上山:その頃にスノーピークのことは調べていたんです。もともとアメリカのブランドだと思っていたんですけど、パッケージの裏を見たら、新潟県三条市って書いてあって、そのときはじめて日本の会社なんだと知りました。
当時は、アップルが初代iPodを出したばかりの時代で、裏面のミラー仕上げを燕三条の職人が実現したということを知っていたので、燕三条は興味の対象ではあったんですよね。ほかにも、柳宗理のカトラリーをここでつくっていたり。
大学4年の2月ぐらいまで就職先が決まっていなくて、スノーピークのホームページをみると開発課の募集があったんですが、新卒不可って書いてあったんです。それでも、面接だけでもしてくださいってダメ元でメールを送ったら、ちょうど新卒も採っていかないとねっていう話がでている時期だったみたいで。履歴書を送って、面接が3月だったかな、雪も残っている時期で、合格通知が来たのが3月20日くらい。それで4月1日入社(笑)。
林・吉野:ありえない(笑)。
上山:その後、上場のタイミングで、会社の強みやビジョンを可視化して伝えていくことをミッションに経営企画部門に異動になり、並行してさまざまな自治体からキャンプ場の改修のご相談をいただく対応をしていた流れで、子会社の「スノーピーク地方創生コンサルティング」の立ち上げと、その子会社の社長も経験して、今に至ります。
林:デザインオフィス、自動車業界、新卒など、いろいろなバックグラウンドのデザイナーが活躍しています。

ロングセラー商品が生まれるまで
――これまで手がけられた商品で印象的なものを教えてください。
林:ぼくはこの『システムボトル 』について。これにはいろいろと思い入れがあるんですよね。
夏の川へ釣りに行ったときなんかに、「冷たいビールを飲みたいなー」という欲求があって、そういう商品がどこかにあるんだろうと思って調べてみたけど、なかったんです。だったら作ってしまおうと。
炭酸飲料って基本的に水筒に入れて持ち歩けないじゃないですか。山や川でビールを飲みたいなって思ったら、氷を入れたクーラーボックスを背負っていかなくちゃならない。山登りや沢歩きには邪魔なわけですよ。

システムボトル
『システムボトル』は、ビール一本のためのミニクーラーなんです。キャップの中に保冷剤を入れることで、缶ビールをまるごと一本冷やした状態で入れておくことができる。
これをひとつ持って行けば、山の一番上や川でビールを飲んで帰って来られる。ザックに入れて、日が高くなったお昼ころにプシュッと開けて、休憩して戻ってくると……そう言っただけで飲みたくなるでしょ?(笑)
吉野:今でも筆圧の薄い林さんのスケッチ覚えているなー。「山登りに、至福の一杯を」って。
林:俺そんなことまで書いてたっけ?(笑)
上山:ありましたよ(笑)。

林:開発にあたっては、こんなに小さい保冷剤なんてなかったので、保冷剤屋さん探しからはじまりました。今ほどネット環境もよくなかったので、探してもすぐに見つからなかったんですよね。日本全国駆け巡って、ようやく静岡で見つけたんです。いまだにこのサイズでご提供いただいています。
あと、これは真空魔法瓶構造になっているんですが、当時は真空魔法瓶がどういった構造なのか知らなければ、どうやって作っているかもわからなかったんです。これは燕市の協力工場で作っているんですが、こういった用途にはどんな仕様にすればいいのかなど教えてもらいながら、すべて二人三脚で作っていきました。そういう勉強がすごく楽しかったです。当然完成したときは嬉しかったですし、発売当時からほぼそのままのかたちでロングセラーとして売れているのもすごくうれしいですね。

コロダッチシリーズ
上山:僕が開発した「コロダッチシリーズ」に関しては、“男のキャンプ用品”というイメージがあったダッチオーブンを、もう少し身近な存在として、1品1品楽しめるようなサイズ感のものとして企画しました。
もうひとつ背景としては、当時から会社のビジョンとして、キャンプだけではなく、日常でも製品を通じて人々の生活を豊かにしたいという思いがあったんです。食はキャンプでもメインイベントですけど、日常的に万人がやっている行為ですので、そこに刺さる商品開発を当時から進めていました。その中で、燕三条の技術を使って、厚さが2.75mmの薄いダッチオーブンを作りました。軽くて小さくて、日常的にも使いやすいキッチンウェアとして、作る側の創作意欲を誘発しやすいように開発しました。
商品化して一番嬉しかったフィードバックは、当時うちの工場で働いていた、地元の組み立てのプロフェッショナルのおばちゃんが、「あんたの作ったあれいいがね!」って言ってくれたことで(笑)。「これで孫に焼りんご作ってあげたよ!」って。全然キャンプをやらない「未キャンパー」にも刺さったことには手応えありました。
林:システムボトルは、「ビールを持っていく」という用途が決まった問題解決型の商品ですが、コロダッチシリーズは、これでなにをつくるかを想像してもらう、提案型の商品なんです。だから逆転の発想なんですよね。

ランドステーション
吉野:僕が開発した「ランドステーション」も、提案型の商品です。これはファスナーがいっぱいついていて、全部広げると一枚の布になるんです。つなげたり離したりしながら、自分で形を変えられる。これは最初は紙でサンプルを作っていましたね。
上山:吉野さんはカバンを作っていたから、平面にこうカット入れることで立体になるんだよっていう風にやっていましたよね。
吉野:いろいろと検証してこういう形になりました。テントはキャンプにとって寝室のようなものですよね。シェルターはお食事をするリビングのようなものですが、これはどこにも属さないんです。
林:こういった新しい考え方の商品を出せるのがスノーピークのすごいところだと思いますね。
企画からデザイン、開発まで 。「すべてはパッション」のものづくり
ーースノーピークで働くデザイナーの仕事の特徴を教えてください。
林:『システムボトル』の企画では、自分で絵を描いてデザインしているんですが、それ以外の仕事の方が圧倒的に多いですね。企画を実現するにあたって、デザインもその手法のひとつですけれど、図面を作ったりものを探したり、モノづくりのプロセスのほぼ全部を開発担当がやります。それがこの会社のユニークなところだと思います。
上山:着想する段階から、一人プロデューサー、一人ディレクター、一人デザイナーなので。その中で七転八倒しながらでき上がる感じです。
林:入社当時はびっくりしましたよ。テクニカルなエンジニアリングや、コストシミュレーションまで担当がやるので。社内で開発を進めるのはひとりなんですが、そのぶん社外の方々と強い結びつきができます。いろんな職人さんと知り合って技術を吸収していくので、一人の企画者、技術者、デザイナーとしての成長できるんです。
そうした幅広い経験から、デザイン以外のことにも興味が出てくるし、財務、営業、コトづくり、街づくりなど、開発のメンバーが別の分野に活躍の場を広げています。

ーー企画について、社内でディスカッションなどは行われていますか?
林:みんなでいろいろアイディアを出して、言いたいことは言い合います。でも、最終的なジャッジは自分です。
吉野:これが都内のデザイン会社だったらできないことかなって思うのは、開発しているもののサンプルあがってきたら、社内から「貸して」って声が上がって、週末キャンプに行って試してみるんです。すると「これ洗うの大変だったよ!」とか、「すごく美味しく焼けたよ!」とか、すぐに意見をもらえる。それが日常茶飯事なんです。新潟という環境を生かした商品開発に直結している。オフィスの横にキャンプ場がありますからね。
林:経営者や上司から「そんなものやるな」と言われることは基本的にないです。
吉野:そこはフラットですね。すべてパッションなんです(笑)。『システムボトル』に関しては、林さんが一番語れますから! 一人でやっていると、熱量があるのでみんなしっかりそれについて語れるんですよ。それはうちの特徴ですね。
林:コストというか、マーケティングに対する意識は他の会社より薄いと思います。おもしろくて、世界中にないものだったら、作ってみて、それがお客さんに受け入れられれば売れるし、そうでなかったら残念だね……という感じで。
上山:採算よりも、目的さえはっきりしていればオーケーなので。
吉野:新しい商品っていうのは、すぐには売れないんですよ。なぜかというと、市場創造型の商品だとどうやって使うのかも分からないし、値段が高いのか安いのかも分からない。鉄の塊で5万もするの⁉︎ってね(笑)。でも我々のロイヤルユーザーさんたちが少しずつそれを使いはじめるんですね。そうすると、開発者が思い描いていた使い方に近いことをしていただいて、「これめちゃくちゃ面白いよ」って発信していただけるんです。
林:吉野さんが作った「ランドステーション」もそうだよね。お客さんが使いはじめてSNSで発信して、別の人が違う使い方をして、あちこちで広まっていったんですよね。
吉野:今でこそSNSがあるけれど、十数年前はブログやBBSをフル活用していました。全然売れないから廃盤にしようか、っていう話が出ることもあるんですが、1年、2年たつとマーケットになる。発売当時はマーケット的に値段が高いも安いもわからなかったものが、それがいつしかスタンダードになっていくんです。
“密度の高い”燕三条のものづくり

キャンプ場に面したスノーピークのヘッドクォーター
林:燕三条はメーカーの密度が高くて、それでいてある領域だけに特化しているわけではなく、かなり幅広い。僕らがお付き合いのある工場はほんの一部で、まだまだ星の数ほどあるんですよね。たぶんこれは、ほかの地域のメーカーさんがやろうと思ったら、ものすごく広域に足を運んでやらなければいけないはずですが、燕三条は小さい地域に固まっているので、「これやりたくて探しているんだよね」って話すと、「◯◯さんならできるんじゃない?」っていう話になったりするんです。
上山:密度は日本でみてもかなりのものだと思います。「工場の祭典」というイベントもあって注目も浴びていると思うんですけど、ものづくりを近い距離で進めていけるので、かなりいい場所なんだろうなって感じます。
林:北陸の方だと伝統的なことをやっている会社が多いんですけど、ここはどんどん未知なものに取り組んでいく、新しいことをやりたがるメーカーさんが多いですね。
スノーピークが提案する「野遊び」の必要性

――スノーピークは「人生に、野遊びを。」というコーポレートメッセージと「人間性の回復」を社会的使命としてかかげられていますが、「人間性」についてどのようなことを考えていますか?
上山:「人間性ってなんぞや」って考えたときに、DNAレベルの「動物」まで掘り下げたものなんじゃないかなと思います。キャンプを通じて新しい友だちができたりするのは、動物としての「群れる」ことであったり、もしくは生きるために「群れる」ことだと思うんです。キャンプというシーンだと、それが遊びとしてできるんですよね。現代社会では、動物的な感覚を使わなくても生きていけますよね。その結果、バランスが崩れてしまうこともあると思うんです。
林:僕は生物としてバランスの良さを保つために「野遊び」が必要なんじゃないかなって思いますね。たとえば、自分がどのくらいの高さの落差を飛び降りれられるのかとか、よじ登ったりできるのかっていうことが、もし外で過ごした経験がないとしたらわからないですよね。そういったことは自然の中に身を置いて経験したことが蓄積していって、感覚が研ぎ澄まされていくと思うんです。子どもの頃の遊びの経験はまさにそうですし、野遊びを通して生物としての人間の限界を学んでいく。それを楽しみながらやろう、というのが我々スノーピークの想いだと思います。
吉野:僕もふたりと同じようなことを考えています。たとえば、仕事で2、3週間忙しくて休めていないと、「よしキャンプに行こう!」って思うんですよね。普通の感覚でいくと、疲れたから家でゴロッとしていようってなるところを、「キャンプしよう!」っていう(笑)。
キャンプに行くと、あたりが暗くなったら自然と眠たくなるんですよね。そして朝4時くらいに明るくなると目がさめる。そうやって都会での生活が一度リセットされる感覚が、人間性の回帰なのかなと思っています。ただそれは、キャンプをしなくてはできないことではないんです。
林:自然を感じる街づくりや旅、グランピング、屋外での研修など、入口はどこでもいいんです。そのためにスノーピークは、体験価値を提供する「コト事業」へとビジネスフィールドを広げていて、デザイナーに求められる役割も、体験デザイン、空間デザイン、コミュニティデザイン、地域や地元プレーヤー、異業種との連携、新しい市場創造、新規事業など、大きく広がっています。求められることは高度ですが、枠にとらわれず、何をやってもいい。広い意味での「デザイン」の力が今、社会に求められているんだと思います。

PROFILE
株式会社スノーピーク
1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。「人と自然、そして人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。新潟県三条市、大自然の懐に、約5万坪のキャンプ場を擁する本社「Headquarters」を構える。コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」。

上山桂 執行役員 経営企画室長 CCPO 兼 経営管理本部長 CFO
2005年、株式会社スノーピーク入社。プロダクトデザイナーとしてアウトドアギアの企画開発を担当。企画開発部門の執行役員を経て、2013年、執行役員経営企画室長。マザーズ上場に携わる。2017年、子会社の株式会社スノーピーク地方創生コンサルティングの設立に関わり、2018年、同社代表取締役社長就任。2019年1月より現職。

林良治 執行役員 企画開発本部長 CPDO
ゲーム・おもちゃメーカーでのプロダクトデザイナーなどを経て、2007年、株式会社スノーピークに入社。企画開発に従事し、のちにロングセラー商品となるLEDランタン「ほおずき」「たねほおずき」や、飲料缶をそのまま入れられる保冷保温機能を備えた「システムボトル」など、数々の画期的製品を世に送り出す。その後、商品本部を経て、現在は 執行役員 企画開発本部長 CPDOとして、ギア・アパレル等の製品開発を含むクリエイティブ部門全体を統括する。

吉野真紀夫 営業本部 東日本事業創造部 シニアマネジャー
鞄やアパレル企業でのファッション小物のデザインに携わった後、2003年スノーピーク入社。入社と同時に東京から本社のある新潟県へ移住。趣味の釣りやキャンプを楽しみながらスノーピークにて商品開発を担当。2012年からは東京にて新規事業関連に従事し現在は、住環境向けのアーバンアウトドア事業の推進とともに、東日本の法人営業部門を管掌。




